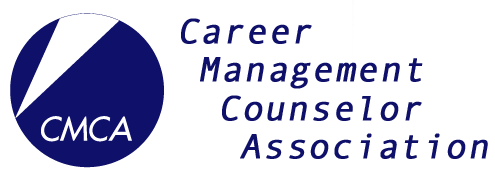共感力を高める効果的なトレーニング
2025年09月11日
2026年01月19日

「相談者の気持ちが理解できているつもりなのに、なぜか心が通じ合えない」
キャリアコンサルティングの現場で、こんな悩みを抱えたことはありませんか。実は、多くのキャリアコンサルタントが直面するこの課題の本質は、「共感」と「同情」を混同していることにあります。
目次
共感力とは何か―誤解を解く
共感とは、相談者の感情を「まるで自分のことのように」感じ取りながらも、「まるで」の部分を忘れない姿勢です。ロジャーズが提唱した「あたかも〜のように(as if)」という概念がまさにこれを表しています。
一方、同情は相談者の感情に巻き込まれ、客観性を失った状態です。「かわいそう」「大変ですね」という反応は、一見優しそうに見えて、実は相談者との間に壁を作ってしまいます。
今日から始められる5つのトレーニング
1. 感情の言語化トレーニング
日常生活で自分の感情を細かく言語化する習慣をつけましょう。「嬉しい」だけでなく、「達成感がある」「認められた喜び」「安心感」など、感情のニュアンスを区別することで、相談者の微妙な心の動きも察知できるようになります。
実践方法: 1日3回、その時の感情を3つの異なる言葉で表現する
2. 観察力強化エクササイズ
カフェや電車内で、周囲の人の表情や仕草を観察し、その人の感情状態を推測します。ただし、決めつけではなく「〜かもしれない」という仮説として捉えることが重要です。
実践方法: 週2回、10分間の観察タイムを設定
3. リフレクションの反復練習
家族や友人との日常会話で、相手の発言を要約して返す練習をします。「つまり〜ということですね」「〜と感じているんですね」という形で、相手の感情を含めて返すことがポイントです。
実践方法: 1日1回は意識的にリフレクションを使った会話をする
4. 視点転換ワーク
ニュースや映画を見た後、登場人物それぞれの立場に立って、その状況をどう感じているか想像します。特に、自分と価値観が異なる人物の視点に立つことで、共感の幅が広がります。
実践方法: 週1本の映画鑑賞後、3人の登場人物の心情を書き出す
5. マインドフルネス瞑想
自分の感情や思考を客観的に観察する力は、共感力の土台となります。毎日5分間、呼吸に意識を向けながら、浮かんでくる感情や思考をジャッジせずに観察します。
実践方法: 起床後または就寝前の5分間瞑想
実技試験でも役立つ共感的応答
実技試験では、共感力が如実に評価されます。以下の段階的アプローチを意識しましょう。
第1段階: 相談者の言葉をそのまま受け止める 「転職を考えているんですね」
第2段階: 感情を含めて返す 「転職を考えていて、不安も感じていらっしゃるんですね」
第3段階: 背景にある価値観や願いに触れる 「今の状況を変えたいという思いと、一歩踏み出すことへの不安の間で揺れていらっしゃるんですね」
共感力向上の落とし穴
共感力を高めようとするあまり、相談者の感情を先読みしすぎたり、自分の経験を重ねすぎたりすることがあります。「私も同じ経験があるのでわかります」という応答は、一見共感的に見えて、実は相談者の独自性を奪ってしまいます。
真の共感は、「あなたの経験は唯一無二のもの」という敬意から始まります。
継続が生む確かな変化
共感力は一朝一夕には身につきません。しかし、日々の小さなトレーニングの積み重ねが、必ず大きな変化をもたらします。相談者から「話を聞いてもらえて楽になりました」「自分でも気づいていなかった気持ちに気づけました」という言葉をいただいた時、あなたの共感力が本物になった証拠です。
キャリアコンサルタントとして、相談者の人生の転機に寄り添う。その責任と喜びを胸に、今日から共感力トレーニングを始めてみませんか。きっと、あなた自身の人生も豊かになるはずです。